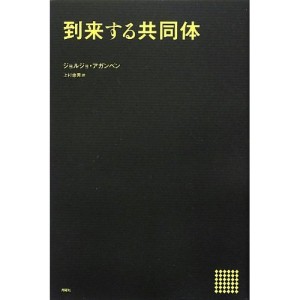「なんであれかまわないもの」
以前少しだけ読んでそのまま積まれていた本「到来する共同体 著:ジョルジョ・アガンベン」をあらためて初めから読み始めて、しょっぱなから「なんであれかまわないもの」という寛容な言葉が登場してきます。
到来する存在はなんであれかまわない存在である。
(略)
〈なんであれかまわないもの〉は、個別ないし単独の存在をある共通の特性(たとえば、赤いものであるとか、フランス人であるとか、ムスリムであるとかといったような概念)にたいして無関心なかたちで受け取るわけではなく、それがそのように存在しているままに[ありのままに]受けとるにすぎない。
そしてこの「そのように存在しているまま」というものはそのまま「愛」というものにつながっていく。
愛は愛する相手のあれやこれやの特性(ブロンドの髪をしているとか、体型が小さいとか、優しいとか、足が不自由であるといったような)に差し向けられることはけっしてないが、それらの特性を愛する相手から無味乾燥な一般性(普遍的な愛)の名において分離することもない。愛は[事物を品質づける]述語のすべてを余すところなく具えた事物を欲する。事物がそのように存在するままに存在することを欲する。愛が何ものかを欲するのは、それがそのように存在するままに存在するかぎりにおいてのことである。これが愛に特有のフェティシズムである。
この言葉を読んで思い出したのが、昨日書いた「植物になって人間をながめてみると 著:森ゆうこ」の中で引用したこの部分でした。
知識を当てにしすぎるのではなく、こと環境に限っては、今は勇気ある積極的な不介入が大事な時期ではないかと思えてくるのだ。(「植物になって人間をながめてみると」P310)
ここで言われる「環境への不介入」ということと、「事物がそのように存在するままに存在することを欲する。」という態度は、とても同じものだと思えます。
環境に対して、分からないものを分かろうとすることであったり、様々な特性に焦点を当て分離分解すること、またそれらの差や多寡などによって価値を図ろうとするようなことよりも、細分化されうる特性を所有している存在そのものを受け入れると言いましょうか。
つまり、「環境への不介入」こそが自然への愛でありえる、と言いえるかもしれません。
そう考えると、「ここになにが存在しているのかを知らなければ保護もできない」という態度を人間関係において置き換えると、「なにもかも知らなければ、愛することもできない」というセリフに変えられそうですね(笑)。